
あなたが選ぶのは、“日本を変える”チャレンジャー? 気付かない果ての“茹でガエル”? ――労働力不足問題のクリティカル・アジェンダに向き合う
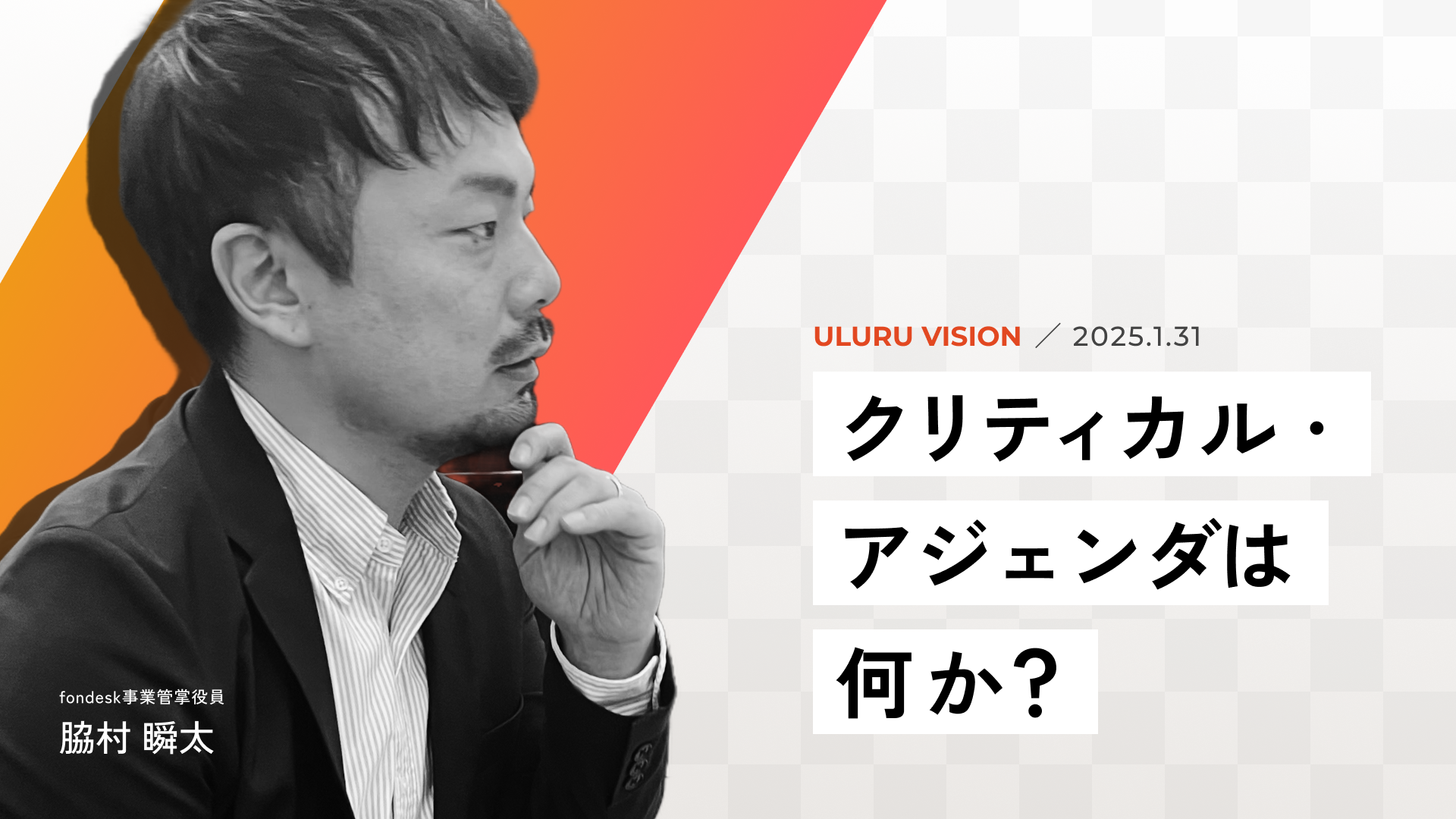
労働力不足のクリティカル・アジェンダ(真の課題)とは――。
うるるの代表・星がホストとなって役員メンバーと議論し、社会に向けて問いかける<Think Critical Agenda>シリーズ。初回に登場するのは、執行役員 脇村瞬太です。電話代行サービス『fondesk』の生みの親であり、現在もfondesk事業 管掌役員を務める脇村の考える、労働力不足問題のクリティカル・アジェンダとは。独自の視点や実務経験と学びから繰り出される仮説に、星がさまざまな角度から切り込みます。
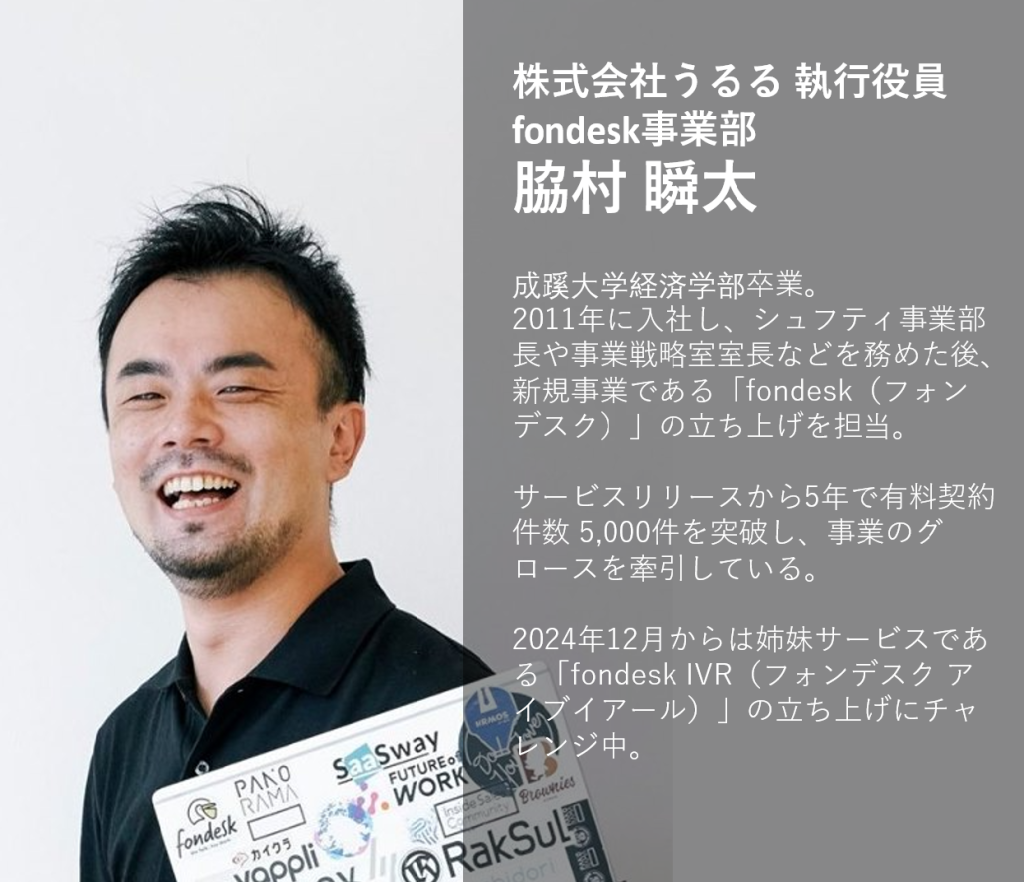
目次
労働力不足問題に向き合うきっかけとなった出来事
星 まずは普段のビジネスや私生活で、労働力不足問題に直面したり、考えるきっかけになったりした出来事を聞かせてください。
脇村 唐突ですが、我が家は子どもの通う学校のPTAを辞めたんです。PTAって僕が小学生の頃から何も変わっていないんですよ。それでも最初の2年は参加しましたが、平日に仕事をわざわざ休んで去年と同じ行事をするための話し合いをすることに不毛さを感じてしまいました。
我が家もそうですが、いまや共働き世帯が専業主婦世帯を上回る時代です。それなのにフォーマットは昔のままなんですよね。これは、労働力不足問題やビジネスにおいても一緒じゃないか、と思っています。日本は人口がどんどん減っていて国際競争力も落ちているのに、旧来の商売の仕方のままでよいのだろうか、と。時代はグローバル化、IT化しているのだから、自分たちも変わっていかなければならないと思っています。
星 私も労働力不足を補ううえでITやAIの活用は絶対だと思います。デジタル化を進めない企業は誰からも選ばれないし、生産性も悪い。座してつぶれるのを待つだけです。けれども、学校をはじめ公共機関はそれで成り立ってしまうんですよね。それでよいのだろうか。ではどうやって改善のためのアプローチをしていけばいいんだろうね。
脇村 いまは山登りのように遅い人に歩幅を合わせている状態ですが、そうじゃなく「先に進むけど、なんとか追いついてね」という考え方が必要です。PTAも違和感を持つ保護者は僕だけじゃないと思うので、変えていこうというムーブメントが起きればいいんですが……。きっかけがないと進まないのかもしれませんね。
星 脇村さんはPTAの問題が労働力不足やビジネスにおける問題解決にも通ずる、という示唆を得たわけですが、改めて労働力不足をどのように観測していますか。
脇村 深刻化していると思いますよ。それこそ介護をはじめ、人的リソースで動いている産業ほど先んじているし、飲食店でも「スタッフのシフトが組めなかったのでお休みします」のような張り紙を普通に見かけるようになりました。ビジネスそのものができなくなるくらい深刻な領域はいっぱいあると思います。他方、うるるをはじめ、IT業界はまだそこまでじゃなく、採用も計画通りできていると思います。成長できない、古い体質から変わることができない会社や業界ほど、労働力不足を顕著に感じます。
星 fondesk事業を通して感じていることはありますか?
脇村 統計によると、コールセンター事業も採用に苦労しているようです。その点、fondeskは、毎月10人、20人とコンスタントに採用できています。これは報酬の高さもさることながら、自宅でできる、つまりは場所に左右されず働けることが大いに関係しているんじゃないかと。fondeskは、コールセンターと仕事内容に大差はなく目新しさもないのですが、「働き方」というフォーマットは現代に合わせています。それが競争力を生み、人材不足にも陥らないことが証明できたと思っています。
星 ところで、電話も昔からあるフォーマットですが、これを無くさない未来を選択した場合の日本のリスクって何だろう? 変わらないでいることで、どんなことが起こると思う?
脇村 いわゆる、ゆでガエルのように変化に気づかないまま、死んでいくんじゃないですかね。(※)
数十年前、中国は「世界の工場」と呼ばれていました。人件費が安く、人もたくさんいるから、日本企業も生産拠点をバンバン中国に建てて、安く大量にモノをつくっていました。ですから、中国に対し、「日本に製品を供給する国」のような認識を持つ人は多かったと思います。けれども、かつての日本のハイテク産業は、いまや多くが中国資本に替わり、メイドインジャパンのテレビやスマホはほとんど売れなくなりました。これって量を軽く見て、「変わることがリスク」と言い続けてきた結果だと思うんです。いまの日本は、日本でしか通用しない規格ばかりだけど、中国は常に世界を見てきたので、開発の早さも改善の早さも飛び抜けています。
※ゆでガエル理論・・ゆっくりと進行する危機や環境変化に対応することの大切さ、難しさを戒めるたとえ話の一種
この先電話も「世界は新しいツールにシフトしたけど、日本はずっと使っているよね」みたいになっていったとしたら、世界のスピードに追い付けなくなるし、日本というマーケットへの魅力も欠くことになると思います。
星 日本は構造や仕組みができているので、切り替えるのが面倒なんだろうね。いまとなっては、切り替えないことのほうが面倒なことに気付いていない。でも、これは「仕組み」で考えるからそうであって、「手段」としてとらえれば、電話が廃れようとも声が聞ける価値はまだまだあると思います。だから、存在自体は悪にはならない。
脇村 また小学生のころの話になりますが、クラス名簿っていま思えば便利でしたよね。クラスメイトの連絡先が分かるから、自分で友だちに電話をかけて遊ぶ約束ができた。でも、いまって何でも親経由なので、親同士がLINEを交換しておかないと始まらない。子どもからしてみれば、不便です。だから、電話のように個人に割り当てられたものが公開されている状態は、悪意のない限り便利なんです。けれども、入手した番号に営業電話をかける目的でしか便利に使えなくなってきているとしたら、文化と使い道にズレが生じているということなので、「不便になってきている」と言わざるを得ない。でも、社長の言うとおり、声が聞けて、その場でつながって用件を伝えられる、聞けることは便益です。
星 救急車を呼ぶときって、やっぱり電話だもんね。となると、これだけ浸透しているものはなかなかなくならない。
脇村 だから、「電話番号」と「電話回線」の価値はそれぞれ分けて考えなきゃならないし、技術はどんどん進化するものの、「通話」というフォーマット自体は、あってもいい。一つの事象を分解して考え、リスクの本質を見誤らないことが大切だと思います。
労働力不足問題におけるクリティカル・アジェンダとは?
星 改めて、今回のテーマである「労働力不足問題のクリティカル・アジェンダ」について、考えを聞かせてください。
脇村 一番の課題は、変化に気付かず、または気付かないふりをして“茹でガエル”のままでいることだと思います。でも、「そうなっちゃダメだ。抗おう、新しい価値を出そう」と励んでいる人はたくさんいます。IT産業で働いている人はみんなきっとそうだし、行政の中にも頑張っている人がいます。ただ、日本って基盤が完成しているから、それをスクラップしてつくりなおすことは非常に難しい。ここも課題の一つであると考えています。
たとえば、エストニアは行政手続きの99%がデジタル化(※)に成功しています。これは、もともと国民が超アナログな生活を送っていて、何も整備されていない状態だったから、自由に設計できたし易く移行できたんです。まっさらな土地なら建物はすぐに建てられるけれど、廃屋が建っていたら持ち主を探して了解を得て、取り壊して、整備して……のように時間もお金もかかる。それと同じです。全部をデザインできる天才じゃない限り、ごっそり変えることができないんですよね。だから、僕たちは少しずつ変えていくしかない。ある程度のまとまりで変えていける人、推進力のある人が立ち上がる必要を感じています。
※本インタビューは2024年12月時点の取材に基づいており、その後の発表により、エストニア共和国の行政サービスの電子化率が100%に達したことが確認されました。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000077316.html
うるるも「企業の労働力不足」という大きな括りの中の、「紙からデジタル」という分野を任せてもらえたなら、良い方向に変えていくためのお役に立てると思いますし、他の分野はまた、その筋のエキスパートに頑張ってもらう。そんな取り組みができたら前に進めそうですよね。何をやっても何十年とかかると思いますが、せっかくやるならば、うるるだからできる問題解決に取り組みたいです。
たとえば、契約書も製本して、割り印を押して、という旧来のフォーマットを変えるのは大変だったはずですが、法令の制約のないものからクラウドサインさんが順番に少しずつ変えて、「さすがに本丸もそろそろ変えていいんじゃないですか」ってロビイングして、ようやく一部変わり始めています。我々の領域もそういう順序を踏みながら、推進力を持って変えていけたら、と思っています。
この問題にどう向き合っていくべきか ”未来への宿題 ー2030年に向けてー”
星 これが最後の問いになるんですが、いまから5年後の2030年、「日本は700万人の労働力を失う」と言われており、経済成長の鈍化など、いろいろな影響が懸念されています。この問題に日本全体としてどう向き合うべきなのか、脇村さんなりの考えを聞かせてください。
脇村 「決まっている未来にはやく行き着く。そのためにはやく変化する」ことが大事だと思います。
2030年、日本は多死社会がいよいよ進み、人口減が顕著になるので、個人的には外国人労働者や移民の受け入れはマストだと思っています。いまも受け入れていないから経済が活性化しない側面があると思うので、今後はこうした社会的ムーブメントがより必要なんじゃないかと考えます。
そして、もう一つですが、「デジタル化」「人口減少」「グローバル化」は既定路線なので、日本企業もそこに資するビジネスをどこよりも速いスピードで開発し、来たるニーズを迎え入れる姿勢が大事になると思います。ガラケーからスマホにシフトするときも、「日常のことすべてがスマホで完結できるようになったら」というニーズに応えたアプリ開発会社やプラットフォーマーが便利なサービスを普及させて、すごく儲かりました。
それから15年が経ったいまの日本は、会社に人がいないからとアウトソーシングに頼り、ニーズをすべて満たせないサービスを渋々選択するような未来を生きざるを得ない状態になりつつあります。企業もまた、コアじゃないものをいかに削いで、経営資源である「ヒト」や「時間」を最大限活用していくことが大事になるでしょう。
fondeskはたまたまですが、コロナの前にローンチしています。当時はまだ、代表電話の初期対応を外部に委託することがフォーマット化されていない時代でしたが、僕らは社会への提案を始めました。その後、コロナ禍では同じようなサービスがいっぱい出てきましたが、僕らはいち早く変化に気付き、アクションしたことによって先行者メリットを得ることができました。この先、世の中はデジタルに置き換わり、効率化は必須になります。ですから、変わるのを待つのではなく、自ら変わるか、もしくは変える側になることが、未来への突破口になると思っています。
うるるも、僕らがする必要のない仕事はどんどん削ぎ落とし、うるるだからするべきことにどんどん集中し、うるるならではの価値をどんどん出していくことを考え、行動を起こしていく姿勢を大事にしていきたいですね。
fondesk事業を通して培われたビジネス感覚をもとに、さまざまな事例を挙げながら、労働力不足の現状分析と労働力不足問題のクリティカル・アジェンダについて終始、星とのテンポの良いトークを展開してみせた脇村。
”変わるのを待つのではなく、自ら変わるか、もしくは変える側になることが、未来への突破口になるーー。”
この言葉はまさに、労働力不足問題を自分事化として捉える思考のヒントにもなり得るのではないでしょうか。次回は、おもいで事業管掌 執行役員の田中 偉嗣が、クリティカル・アジェンダと向き合います。

