
成果を生み続ける仕組みと情熱あふれるチームの力で、Govtech市場を疾走中!【Govtech事業本部セールス部座談会】
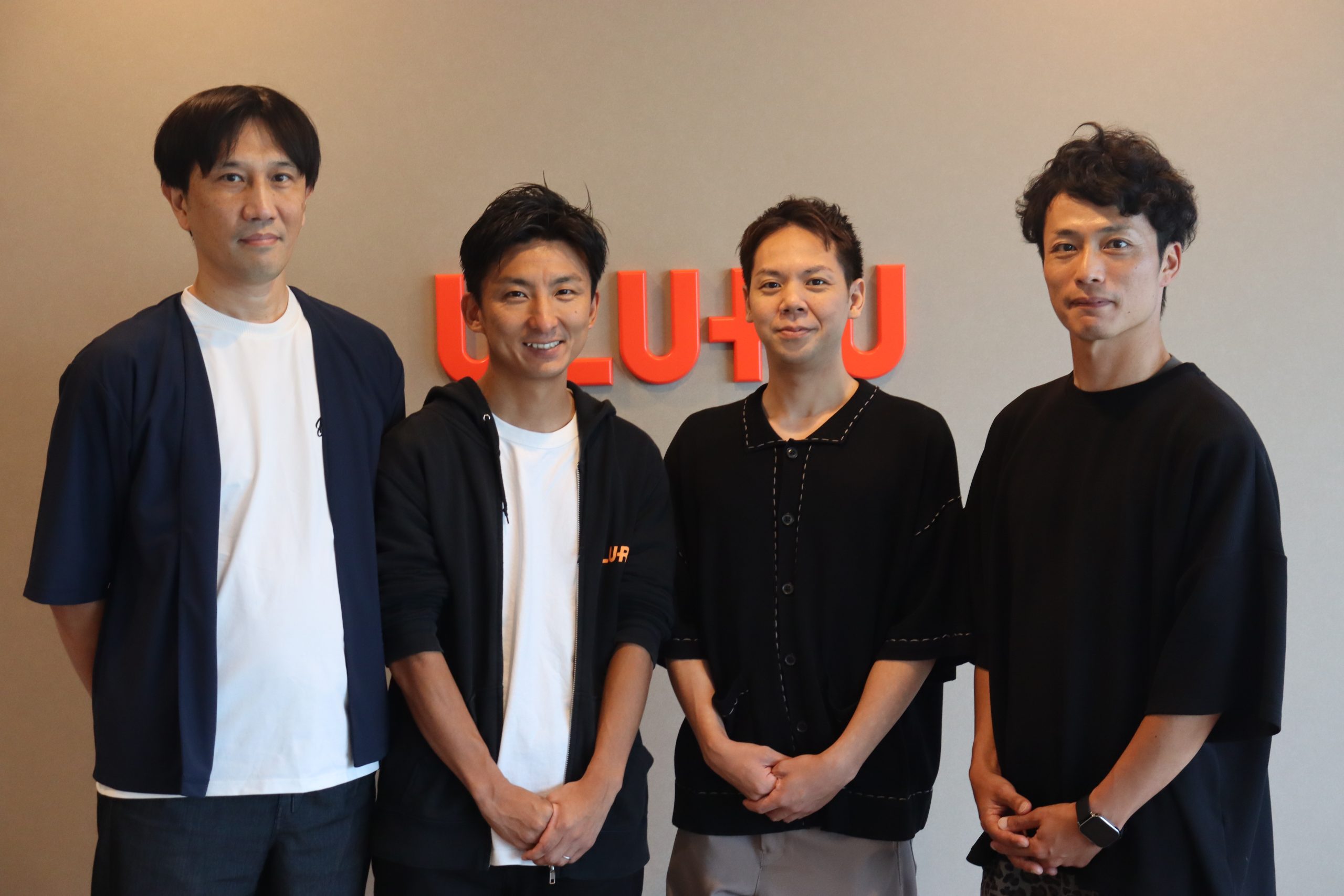
うるるの屋台骨を支えるGovtech事業本部。ここでは、入札情報速報サービス『NJSS(エヌジェス)』をはじめ、自治体官公庁と民間企業をつなぐさまざまなプロダクトを扱っています。そのビジネスの最前線で活躍しているのが、セールス部のメンバーたち。なかでも、フィールドセールスと呼ばれる、セールス1課、セールス2課、そしてアカデミー課では、インサイドセールスからの情報をもとにお客様と直接対峙し、お客様の課題やニーズによりそった提案を行っています。
このたび、セールス部の新しいビジョンが定まったことを機会に、部長の竹森聡さんがフィールドセールスの各課長を招集。過去の成功と未来への展望を交差させながら、仕事への熱い想いを語り合いました。
▼座談会メンバー
竹森 聡
Govtech事業本部 セールス部 部長
セールス部責任者。事業部全体の短期、中長期的なミッションを成し遂げる役割も持つ。栗原 博晃
Govtech事業本部 セールス部 セールス1課 課長
新規受注の獲得がメインミッション。主にIT業、クリエイティブ業のお客様を担当。齋藤 真史
Govtech事業本部 セールス部 セールス2課 課長
新規受注の獲得がメインミッション。主に建設業、清掃業、警備業のお客様を担当。野口 翔
Govtech事業本部 セールス部 アカデミー課 課長
入札未経験のお客様に入札に関する知識を提供する「入札アカデミー」を担当。
目次
うるるの成長エンジン、Govtech事業本部セールス部
竹森 今期からのGovtech事業本部の新しいビジョンが決まりました。本部内ではさらなる成長を目指していこうという機運が高まっていますが、このタイミングは私たちがどんな歴史を歩んできたのか、そして現在はどんな取り組みをしていて、未来に何を目指していくのかを話し合う良い機会になると思い、皆さんに集まってもらいました。
苦労も紆余曲折もあったけれど、みんなで乗り越え、成功をつかんできたその過程を整理しつつ、セールス部の強みを改めて明らかにできればと思っています。
そんなGovtech事業本部は、うるるの中でも売上の多くを占める重要な部門であり、人も予算も潤沢に割かれていることから、皆さんも常に責任の重さを感じていると思います。ただ、それは期待の表れでもあって、全員で大きな目標に挑戦できるやりがいや達成できたときの喜びもひとしおではないでしょうか。
扱うサービスも、主力の『NJSS』を皮切りに、官公庁ビジネスを上流工程から支援するプラットフォーム『GoSTEP』、入札資格を管理する『入札資格ポータル』、公的機関向け購買調達サービス『調達インフォ』と、少しずつ広がってきました。そのどれもがNJSSをよりよく使っていただくことを念頭にニーズを先回りしてつくってきたものですが、皆さんはこれらのサービスを手に、普段からお客様にどんな働きかけをしているのか。これは栗原さんに話してもらおうかな。

栗原 私たちは、日々お客様と向き合うことが一番の業務です。ただ、商談ではサービス云々を話すのではなく、これらのツールを使った先でお客様のビジネスがどのように飛躍するのか、その視点を大切にしています。そのため、お客様とは2回3回と対話を繰り返しながらご提案するのが、基本の営業スタイルです。また、お客様の業種はさまざまなので、個人の知見では足りない部分はメンバー一人ひとりのナレッジを集約し、チームで共有しながら進めています。
セールス部のメンバーは、現在40名ほど。公共事業経験者はほとんどおらず、誰もが未経験からのスタートです。
「コロナで訪問営業できない」が、セールス部の歴史を変えた
竹森 今日は、セールス部の歴史を紐解くことも目的の一つにしていて、私の知らない話も出てくるんじゃないかと期待しています。そこで、所属歴が一番長い齋藤さんからいろいろと聞かせてもらえたらと思うのですが、まず当時はどんな雰囲気でしたか?
齋藤 私が入社した9年前は、オフィスから地の利の良い東京23区のお客様を訪ねて商談を行うチームと、地方を含むそれ以外のエリアのお客様に電話商談を行うチームの二つに分かれていました。
部の考え方も、一人ひとりが個人目標を達成できれば、チームの目標も自ずと達成できる、というものだったので、営業スキルや商材知識などすべてが属人化している状態でした。実際、私も1か月の初期研修を終えたら、先輩の商談に同行して流れやトークを覚え、3か月目からは一人でお客様のもとに伺っていました。
このころは一つ終われば、また次へと移動しながら1日に四つくらいの商談をこなすので、週の半分は直行直帰、オフィスに戻ってもチームメンバーと顔を合わせるタイミングがなかなかない、というのが日常でしたね。

竹森 やはり、いまとはだいぶ違いますね。当時はかなりの個人主義、成果主義でしたよね。
齋藤 そうですね。営業の流れ自体は、無料トライアル登録をされたお客様にインサイドセールスがアポを取り、私たちが訪問して受注につなげるというもので、いまとさほど変わらないのですが、目標が常に上方更新されることもあって、達成し続けることが難しい。それに当時は受注件数を伸ばすことを重点目標に置いていたので、契約期間をお客様が選べたりと柔軟にしていました。
ただ、このままでは売上が鈍化してしまうことが明らかだったので、ある時期から単価アップを目指す方針に転換しました。契約期間も固定化し、使える機能によって料金プランに幅を持たせたり、初期費用を導入したりと、さまざまな施策を打ち出すことで目標を達成してきました。
竹森 そのなかで迎えたのがコロナでしたが、ここはセールス部の歴史の中でも一番の正念場になりましたよね。
齋藤 コロナの影響は大きかったですよね。
竹森 いままでのような営業ができなくて、苦労も多かったんじゃないですか?
齋藤 当時は、お客様のもとを訪問できないどころか出社もままならず、これからどうなるんだろうと不安だらけでしたし、商談もオンラインに早々と切り替えたはよいものの不慣れなメンバーも多く、成果は出るのだろうかと危惧していました。しかし、これらは杞憂だとすぐに分かりました。というのも、多くの企業がコロナによる経営の先行き不透明さから安定感のある公共事業に目を向けるようになり、無料トライアルが爆増したのです。さらには、オンラインになったことで移動時間が無くなり、いままで以上の商談をこなせるようにもなりました。私も当時は商談の連続で、1日8枠を1週間続けてこなすような時期もあったほどです。
竹森 時間の使い方が変わったことによる効果って、他にもありましたか?
齋藤 課内コミュニケーションがずいぶん活性化されたと思います。以前はミーティングをしようにも、スタートは夕方以降ということが多かったのですが、日中でも時間を合わせて実施できるようになり、さらには夕礼を始めたりと、メンバーと接触する機会がグンと増えました。新人メンバーの商談に同席しやすくもなり、育成促進の面でもプラスになりました。
竹森 営業体制を現在に近い形に再編したのも、この頃でしたよね。
齋藤 そうですね。ターゲット戦略を打ち出し、お客様のセグメントがそれまでのエリアから、業種や入札経験の有無へと変わりました。その結果、メンバー一人ひとりが知識を深めやすく、お客様にも的確な説明やアドバイスができるようになり、全体のボトムアップにもつながっています。
そして、このあとすぐでしたよね? アカデミー課が立ち上がったのって。
野口 2022年に誕生しています。アカデミー課とは、入札アドバイザーによるセミナー『入札アカデミー』を実施するチームであり、入札の基本知識から入札に成功するノウハウまで、さまざまな知見をお客様に提供しています。
誕生の背景にあるのは、入札経験のあるお客様ほどNJSSに価値を感じていて受注につながりやすい一方、未経験の場合には受注率が低いという事実です。たとえ契約に至ったとしても解約率が高く、課題は散見していました。しかし、マーケットを拡大していくためには、入札未経験のお客様の受注を増やすことが必須です。そこで、入札未経験者の課題解決の専門集団として、アカデミー課が生まれたのです。

竹森 これは、セールス部にとって大きいトピックになりましたよね。受注件数も120%アップと良い結果が出ています。
野口 「未経験のお客様を受注につなげるには、NJSSの価値を実感してもらう必要がある」という仮説が見事にはまりました。
ただ、私たちは「NJSSを売り込むな」をテーマにしているので、サービスの話は積極的に行っていません。まずは入札参加に興味を持ってもらうこと、入札参加に向けた準備の伴走を念頭に置いています。そのための教材としてNJSSを活用しているので、アカデミーを卒業されるお客様から「NJSSを使いたい」と言っていただくことをゴールに長期的視点をもって取り組んでいます。
「チーム」を主語に活躍するメンバーを支える独自の研修プログラム
竹森 コロナを経てセールス部を取り巻く環境は大きく変わってきたわけですが、メンバーの取り組み姿勢を見ていても、みんなひたむきだし、向上心も年々高まっているように感じています。なかでも、協働意欲の高さは目を見張るものがあるというか。私は数社経験してから、うるるにジョインしたのですが、ここまで意識の高い組織は初めてです。
栗原 それって、どういうシーンで感じています?
竹森 セールス部は個社ごとに担当制を敷いていますが、お客様の反応が徐々に鈍くなり、担当者が架電してもつながらない場合には、「代わりにかけてみましょうか」と誰となく手が挙がったり、お客様からのイエスがなかなかもらえないメンバーがいれば、「私が同席して、フォローします」と申し出があったりと、自分の成績にならないことでもいとわず率先できる人が多いですよね。まさに、うるるスピリットの一つ『会社はホーム 社員はファミリー』が強く体現されている部分であり、カルチャーフィットを重視したうるるの採用戦略が活きているとも感じます。
ちなみに、栗原さんから見て、セールス部で活躍している人の共通項ってどんなところにあると思っています?
栗原 協働意欲の高さに加え、素直な人、共感力や傾聴力の高い人、さらには周囲を巻き込んで物事を推進できる人が、コンスタンスに成果を上げていると感じています。自分一人ではなく、チームという枠組みをうまく活用できることが、活躍するためのポイントなんだろうな、と。

竹森 たしかに。本当にメンバーは誰しも、スキルを上げていきたいと強く思っていることをひしひしと感じます。ですから、その想いに応え、支援していくこともまた私たちの使命の一つです。
その点、今期からは営業力をさらに伸ばすことを目的に、事業本部独自の育成プログラムをスタートしました。ここでは、営業パーソンの育成に必要な要素を100項目洗い出し、それぞれに目指す到達点を設定しているほか、25人いるフィールドセールスメンバーを三つに分け、階層別研修を行っています。全員がハイプレイヤーを目指していこうという風土づくりにも力を入れていますが、実際、メンバーはどう思っているんだろう? 意見や感想って届いています?
齋藤 「自分の成長につながっている」「商談で良い結果が出るようになった」のように、手応えを感じているようですよ。
野口 「相手の習熟度や理解度を踏まえたコミュニケーションの重要さに気付ける体験ができる」という声も聞こえています。これは研修の中のお互いに育成し合うカリキュラムに対する感想ですが、それぞれにいろいろな気づきがあるように思います。
竹森 それはうれしいですね。育成プログラムによって成長できる環境が整いつつあるので、目標設定の見直しも急ぎたいですね。
これまで評価は、目標を達成できたのかどうかが判断軸でしたが、今後は目標を追う過程でどういうアクションを取ったのか、そのなかでどういう行動変容があったのか、再現性のある仕組みをつくることができたのか、をフォーカスするほうに移行していきます。いわゆる成果主義から一転したことで、メンバーのストレスが軽減したり、自己研鑽に時間を割けるようになったりと、すでに良い効果が出ていますから、安心して活躍できる組織づくりをますます進めていきたいです。
個人を起点に組織の強みをつくる

竹森 最後に、セールス部のやりがいや醍醐味を一人ずつ聞かせてください。まず野口さんはどんな瞬間に感じていますか?
野口 一番の醍醐味は、自分の成長とチームの成功を同時に感じられるところです。そして、うるるの屋台骨であるNJSSの営業として第一線で会社に貢献できることも大きなやりがいですね。
齋藤 私は、お客様ご自身がまだ気づいていない課題を見つけ、NJSSを解決の糸口として結びつけられたときに、やりがいを感じています。また、お客様からの「NJSSのおかげで、新しい販路をつくることができました」「関連会社でも導入したいのですが」といった言葉は一番の励みであり、いつも心の中でガッツポーズをしています。
栗原 私にとっては、できなかったことができるようになったときが醍醐味です。受けたフィードバックを実践して成功体験を積むことが自分の引き出しを増やすことになりますし、その積み重ねでスキルが上がっていくと、結果的にチームの底上げになります。個人を起点に組織の強みをつくれる点は、セールス部の持つ面白みの一つではないでしょうか。
竹森 今日は、セールス部の歴史やターニングポイント、それから皆さんの仕事への想いを共有できる、とても良い時間になりました。
繰り返しになりますが、Govtech事業本部は、株主様、お客様、そして、うるる社内から大いに期待されている組織であり、セールス部はそれを背負って成長し続けることが求められています。しかし、NJSSがどんなに素晴らしいサービスであったとしても、メンバーのモチベーションを高く維持できないことには、売上にもいつか頭打ちが来るでしょう。全員が長く活躍するためにも、セールス部の新しいビジョンである「一人ひとりが強いリーダーシップとフォロワーシップを発揮して、メンバー全員の才能と情熱が発揮され続ける組織」のもと、人の成長支援に力を注ぐと同時に、現状に満足することなく、さらなる事業成長を目指していきたいものです。ここを新しいスタート地点に、引き続き力を合わせていきましょう。
—–
座談会は、セールス部が自治体官公庁と民間企業の架け橋として、Govtech事業本部とうるるの成長をけん引してきた歴史をはじめ、お客様によりそい、課題を解決していくフィールドセールスの仕事の魅力、さらには、セールス部を率いるリーダーたちの本音と情熱を知れる、またとない機会となりました。
新ビジョンに向かって新たに走り出した、今後のセールス部の活躍にぜひご注目ください!

