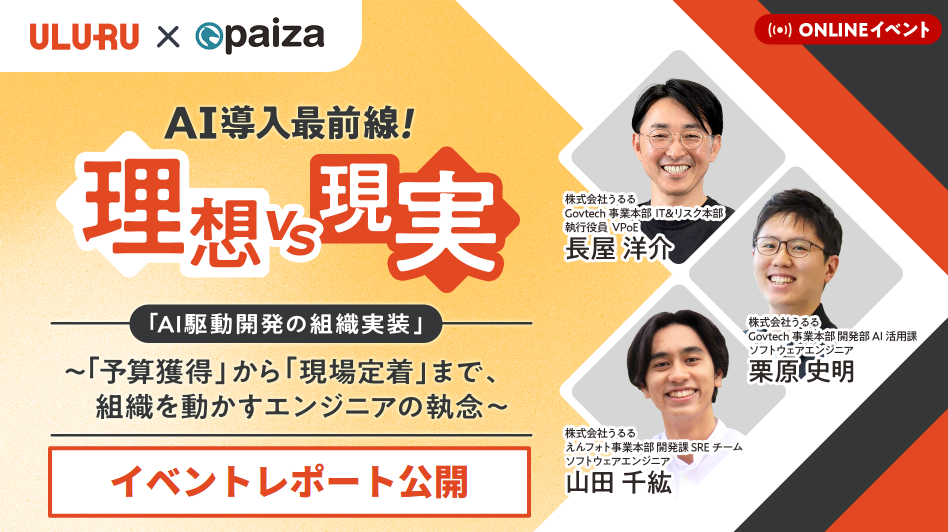
男性育休は組織に何をもたらしたのか――。その意義と現場のリアルに迫る<育休取得者篇>
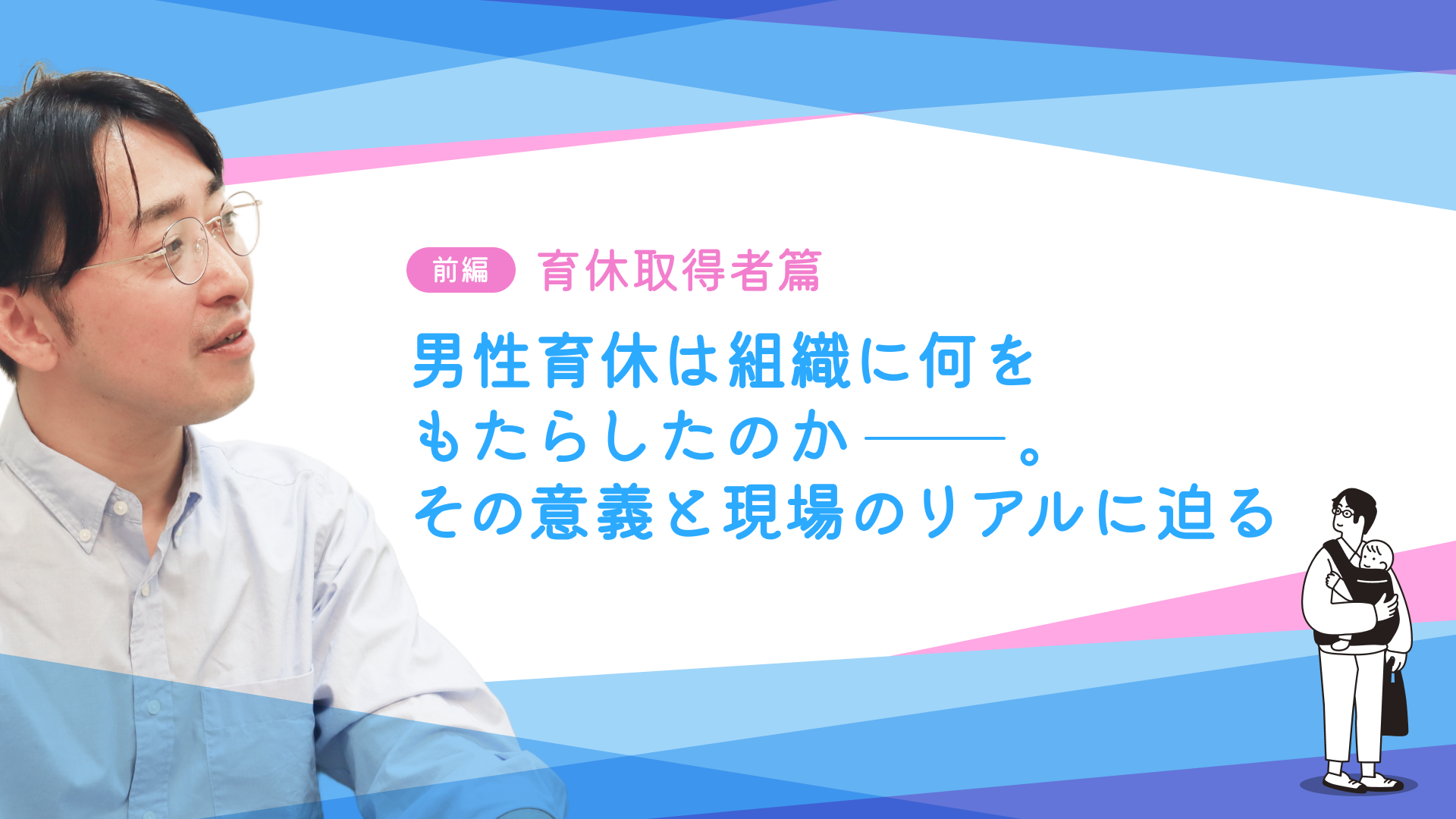
厚生労働省が実施した、「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」では、若年層の87.7%が育休を取得したいと回答し、その内訳は、男性が84.3%、女性が91.4%と、男女間であまり大きな差がない結果がみられました。
また、同省の調査によると、昨年度の男性の育休取得率は30.1%を超え、男性の育休取得への世間的な関心はさらに高まりつつあります。
こうした中、うるるでもついに、取締役として初めて男性が育休を取得しました。
育休を取得した本人と留守を預かったチームメンバーは、育休期間中、どのようなことを感じたのでしょうか。本記事では、双方が得た学びや成長を深掘りすることで、男性育休の価値に迫ります。前編となる今回は育休を取得した、取締役長屋洋介のインタビューをお届け。フレキシブルな働き方や、多様な人材が活躍できる環境が求められる今、男性育休がもたらす気づきやヒントを探ります。
参考:
●若年層における育児休業等取得に対する意識調査(速報値):https://www.mhlw.go.jp/content/001282074.pdf●「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値):https://www.mhlw.go.jp/content/001128241.pdf
インタビュイープロフィール

1978年10月31日生まれ。 2008年よりうるるへ参画。
開発部門立ち上げや事業管掌を経た後、現在はITとルールを管掌し、効率的かつ安全に働ける会社づくりに注力。
たまたまコロナ禍で育児をスタートし、「子どもと関係性を築く時間が取れたことはとても幸運」と話す。
目次
「男性育休を取得しやすい会社に」決意の一歩を踏み出した
――育休取得に至った経緯と決断の背景を教えてください。
我が家では、妻が帝王切開での出産が決まっており、産後1か月間は自宅で静養する必要がありました。そのため、上の子どものケアと新生児のお世話を同時に行うのは妻一人では難しいと考え、夫婦で話し合った結果、私も育休を取得することを決断しました。
実は第一子が生まれるとき、妻から育休をとることはできないか聞かれたのですが、そのときは即答で難しい、と答えたんですよね。「役員だし、無理だろうなあ」と。会社に掛け合うこともしませんでした。ですが、今回はこうした事情がありましたし、妊娠が判明する前に「育休を取得することの意義」を強く感じた出来事があったんです。
それが昨年6月に参加した、外部の多文化交差型トレーニングという講習です。このトレーニングでは、「女性の健康」「外国籍社員のインクルージョン」「LGBTQ+」などをテーマにDE&I推進を学び考えるものですが、その中の一つに「男性育休取得」がありました。
この場で、育休取得を推進してこなかった経営者の多くが悔やんでいること、同僚に負担がかかることを気にして取得を言い出せないケースがあることを知りました。それと同時に、自分も第一子のときにちゃんと育児に対して正面から向き合うことができていたか?振り返るきっかけにもなり、それなら、まずは言いやすい状況をつくること、安心して休める体制をつくることが必要だなって、その時思いました。
一方で、「収入を減らしたくない」「親に手伝ってもらえる」という理由で、育休を必要としない人も一定数いることが分かり、男性育休は取得率を高めることが目的ではなく、取りたい人が取れるようにすることが大事なんだと理解しました。
そして講習を受けた約半年後、2024年1月に妻の妊娠が発覚し、これらを実現する最初の一歩として、まずは自分が取得しようと決めました。
社長に相談したところ、開口一番の言葉は、「そこは時代の流れに逆らわずにやろう!働きやすい会社をつくろうよ」でした。この言葉で改めて経営層として、言いやすい空気感をつくる責任を改めて感じることができました。
一つ上の仕事を渡すことで、安定したチーム運営を実現
――仕事の引継ぎはいかがでしたか?
引継ぎらしい引き継ぎはやっていません。育休の取得を経営層や自チームに公表したのが5月頃でしたので、猶予期間はおよそ5か月ほどありました。
僕は2週間休んで、2週間時短勤務をしたのですが、猶予期間が十分にあったことと、普段から課長の2人に業務の一部を分散していたこともあり、業務上の不安はあまり無かったですね。これをしていなかったら育休取得は選択できなかったと思います。
IT&リスク部は、僕が部長を兼務していることもあり、普段から、「他の人でもできるようにする」「二人できる人がいればお互いに助け合える」という考えのもと、リーダーは課長の、課長は部長の仕事を共有することを意識しています。
私の管掌部門は、各課がまとまった単位の会社機能を担っているため、各機能ごとに戦略・計画・予算を作成する必要があると考えています。
そして、ロミンガーの法則(「人が成長する7割は業務経験、2割が薫陶、1割は研修である」)にもある通り、人は経験の中で成長するという考えに基づき、戦略・計画・予算づくりにおいては、部長になってから取り組むよりも、課長時代から取り組み準備していった方が、良い部長を体現できる確率が上昇すると、私自身の経験からもそう考えています。
とはいえ、いきなりできるようにはならないので、対話を重ねて判断軸をつくり、視野を広げられる働きかけをていねいに行っています。すると、そのうちに勘どころができて自信も付くんですよね。最初は「どうしたらいいですか?」だったのが、自然と「このように進めようと思うんですが、いいですか」になり、僕も「この仕事は任せているから決めていいよ」って言えるようになります。
こういった小さな積み重ねが、やりがい、成長などの側面にも大きく影響すると考えています。
ですから、育休取得にあたっても、僕は「任せたよ」みたいな心持ちでしたし、本人たちも「不安はない」とのことだったので、申し送りは「緊急時は電話してね」くらいでした。
育休取得が特別なことではなく、「自然な選択肢」として認識される企業文化を
――はじめての育休生活は、いかがでしたか?
赤ちゃんの顔を眺めたり触れたりする時間が多くあったことは、とても良かったです。第一子のときにはできなかったので、この時間はとても大事なものだろうなと感じていました。
一方、時短に入ってからは大変でした。育児にプラスして仕事があるんです。緊急で対応しなければならない仕事があるのに、上の子が泣いていたり、下の子の具合が気になったりすると、コントロールしきれない。もう嫌だって思う瞬間が正直ありました。このときは僕の親に来てもらって、「一人になりたいです。サウナに行ってきます」って出かけていました。一人の時間って必要なんですよね。妻もしかりで、美容室とかどんどん行ってもらおうって思うほど、その大切さを知ることができました。子育て中の親御さんへの尊敬がさらに深まりました。
――経営層が率先して育休を取得することで、企業文化にどのような影響を与えると考えますか。また、男性育休の取得推進のために、どのような取り組みが必要と感じていますか。
うるるの若手男性が男性育休を取得していく事例や、男性育休に関するニュースを拝見していると、若い世代にとっては、男性も育休を取る選択肢のあることが当たり前になりつつあると感じています。
また、私自身の家庭での実体験を踏まえると、昨今では出産を控える夫婦の間で、男性の育休について話し合うことが、以前に比べてごく自然な話題になっていると感じています。
そのため、経営層が率先して育休を取得することは、育児と仕事の両立を推進する企業文化のみならず、フレキシブルな働き方を受け入れる組織風土や多様な人材が活躍できる環境の醸成に大きく影響を与えると考えています。
従業員が会社を選ぶ時代のいま、「給料がいい」「福利厚生がいい」のような条件面だけでなく、自己実現を目指しながら長く働ける道筋を示せる企業でありたいなと思っています。
そして、男性育休の取得推進のためには、「①言いやすい空気感をつくること」、「②メンバーが不在でも回るような組織づくり」が重要だと考えています。
1つ目は冒頭から一貫して言い続けていますが、これは、経営層のみならず、マネージャーなどの管理職メンバーからの理解と協力も欠かせません。管理職が育休取得を上手に受け止め、個々の選択を尊重する姿勢が、全体の雰囲気を変える鍵になると感じています。
2つ目の、メンバーが不在でも回るような組織づくりですが、育休取得の大きな障壁の一つは、業務の滞りや引継ぎ負担です。この課題は一朝一夕で解決するものではないため、普段から業務の属人化を防ぎ、引継ぎコストを減らす仕組みづくりが重要です。たとえば、情シスではすべての業務を細かくリストアップし、業務の見える化を行いました。この取り組みによって誰がどの業務を担当しているかが一目で把握でき、担当の不在時にも適切なフォローができるようになりました。
こうした環境整備によって、育休取得が特別なことではなく、「自然な選択肢」として認識される企業文化を構築できると考えています。結果として、従業員がライフイベントを安心して迎え、長期的に活躍できる持続可能な組織へとつながるのではないでしょうか。
育休で改めて感じる家族の大切さ。育休取得の意義ー
――最後に、育休を取得してみての改めての感想をお願いします。
家族の増えるこの大切な機会を、家族と一緒に過ごせたことは、僕にとって家族との絆をより深められる良い経験になりました。赤ちゃんと過ごす時間を家族と共有できたことはもちろんですが、何よりも、育児の大変さを第一子のときよりもリアルに感じられたことが大きかったと思います。特に、赤ちゃんのお世話が想像以上に体力や気力を必要とするものであると、改めて実感しました。育児に集中していると、親である自分も心身ともに疲れてしまう瞬間が少なからずあります。だからこそ、パートナーが明らかに疲れているときや大変そうにしているときは、遠慮せずに育休を取得して家族を支えることがとても大切だと感じました。
また、最近、他の男性社員が育休を取得することを決めたという話を聞きました。自分が育休を取得したことが、こうして次の事例をつくる一助となれたのなら、心から「育休を取ってよかった」と思えます。このように、育休取得が当たり前に広がり、次々と新たな事例が生まれていくことで、さらに育児と仕事を両立しやすい企業文化が少しずつ築かれていくのではないかと感じています。
編集後記
育休取得は個々の家庭や仕事の状況によって選択が異なるものですが、重要なのは、”取りたい人が安心して取得できる環境”を整えることです。今回の取締役 長屋の育休取得を一つのきっかけに、うるるがさらにフレキシブルな働き方を推進し、多様な人材が活躍できる企業として成長していくことを期待しています。
次回は、取締役の育休中にチームを支えたメンバーたちの視点を通じて、育休取得がもたらす組織の変化や学びについて深掘りします。どうぞお楽しみに。

