
【C-hub Meetup Vol.3イベントレポート】自治体DX推進計画の実行現場 計画と現場のギャップをどう埋める?

2025年5月、うるるは、自治体DXの推進におけるキーパーソンであるCIO補佐官が、悩みや課題、取り組み事例などを気軽に共有し、横のつながりを育む実務者視点のコミュニティ「CIO補佐官HUB(略称:C-hub)」を発足しました。現在、月1回のペースでCIO補佐官がリアルに集い語り合う「Meetup」を開催しています。
7月16日に行われた第3回のテーマは、「自治体DX推進計画の実行現場 計画と現場のギャップをどう埋める」。全国各地のCIO補佐官ら14名が集い、計画策定過程における自治体職員との関わり方、ギャップとの向き合い方、考え方まで、ご自身の経験をもとに闊達なディスカッションを繰り広げました。
本記事では、当日の様子をレポート形式にてお届けいたします。
▼Meetup Vol.1のレポートはこちら
【イベントレポート】CIO補佐官HUB Meetup Vol.1 開催レポート~自治体DXを担うキーパーソンが語り合った「CIO補佐官の理想の姿」
▼Meetup Vol.2のレポートはこちら
【C-hub Meetup Vol.2イベントレポート】自治体DXの現場から学ぶ、CIO補佐官の信頼構築ナレッジ4選
▼「CIO補佐官HUB」の詳細については、プレスリリースをご覧ください。
自治体DXのキーパーソン「CIO補佐官」初のコミュニティ『CIO補佐官HUB』始動 横の連携を通じて、全国のDX推進力の底上げを目指す ~
Meetup Vol.3参加者紹介:
翁 財将 氏
京都府宮津市 CIO補佐官木村 礼壮 氏
衆議院事務局CIO補佐官兼最高情報セキュリティアドバイザー小林 啓男 氏
茨城県那珂市CIO補佐官・小山町CDO下山 紗代子 氏
愛媛県松山市CIO補佐官冨岡 周泰 氏
福島県南相馬市・沖縄県浦添市 CIO補佐官福田 次郎 氏
神奈川県横浜市 CIO補佐官森谷 靖男 氏
独立行政法人農林漁業信用基金 CIO補佐官若生 幸也 氏
福島県南相馬市・東京都府中市・兵庫県三田市・山口県宇部市 CIO補佐官桶山 雄平
徳島県小松島市 CIO補佐官(うるる取締役副社長、うるるBPO代表取締役社長)櫻井 俊寿 氏
総務省 自治行政局地域政策課 地域情報化企画室 地域情報課 第三係長司会進行 蓑島 智大 氏
カントミント株式会社 取締役CFO
元・札幌市 デジタル戦略推進局 デジタル企画課 企画係長※順不同

目次
DX推進計画策定におけるCIO補佐官の関わり方

最初の話題は、DX推進計画策定段階でのCIO補佐官の関わり方について。参加者からは「全体方針をつくる場面に関わっている」「つくるための材料を提供し、実務は自治体職員に任せている」「職員が作成したものに対するレビューと、計画を具現化していく段階での助言をしている」といった声があがり、あくまでも主体者は自治体という構図を保ちながら関与している様子がうかがえました。
このほか、「職員からの提案を批評するのではなく、皆さんの考えを聞き出し、実現したいことへとまとめていく。そんなファシリテーターに近い立場を意識している」「DX推進には職員のトランスフォーメーションが必要という考えのもと、人材育成計画も一緒に策定した」といった、ご自身のスタンスや、計画を補完する取り組みに臨んだケースを話す参加者もいました。
計画を立てるか否か、CIO補佐官の数だけある多様なアプローチ

一方、策定の前段として、「そもそも計画をつくるのか。この議論を深める必要がある」と答える参加者も。実際、つくらない選択をした自治体でCIO補佐官を務める参加者は、その意図をこのように説明します。
「ここは人口数万人の自治体ということもあって、この街にとって、もっと必要なことに人的リソースを割く、という選択をしました。だからといって何の取り組みもしないのではなく、首長以下、全職員にDX研修を実施し、その場で職員の抱える課題をすくいあげ、私からの助言や提言をしているほか、自治体システムの標準化など、やらなければならないことにも取り組んでいます」
ほかの参加者からも、「DX推進を主導できるなら策定は不要」という意見や、DXにまつわる通り一遍を計画に網羅するのではなく、自治体の状況に合わせる――たとえば、職員の業務負荷が高い場合には、市民サービス向上よりも、その解消を徹底して行うことが先決、という声もあがります。
そのようななか、聞こえてきたのは、「計画策定は、事業立案や業務見直しのよい機会。あえて時間を取ってつくるという考え方もあっていい」という意見。実にさまざまな考え方が示されました。
ギャップは起こるもの。その時どうするのか、が大切

話題は今回のテーマの核心である「計画と実行のギャップ」へ。計画に対する進捗に遅れが出ることもあれば、計画を立てることが目的になって実行が進まない場合も。参加者は、これらのギャップをどう受け止め、対処しているのでしょうか。
まず、誰もが異口同音にしたのが、「ギャップは起こることが前提」というもの。以下、参加者の意見です。
「大事なのはそのギャップを認識できること、そして、軌道修正できる計画になっていることだと思います」
「計画通りに進まないのはダメだ、という考えを取っ払う。むしろ、進まないときの修正力こそ大事なんだっていうコミュニケーションを取るようにしています」
「ギャップが生まれることよりも、定めた方向に現場が向かい続けることのほうが重要だと思います」
「よくあるのは、工程表に落としたものの、進め方が分からず手が止まってしまうことです。だからといって、一つひとつをCIO補佐官が組み立てるわけにはいきません。いかに職員自らが考え、行動に移すのか。CIO補佐官はそれを引き出すアプローチに努めなければならない、というのは皆さん同じ考えだと思います」
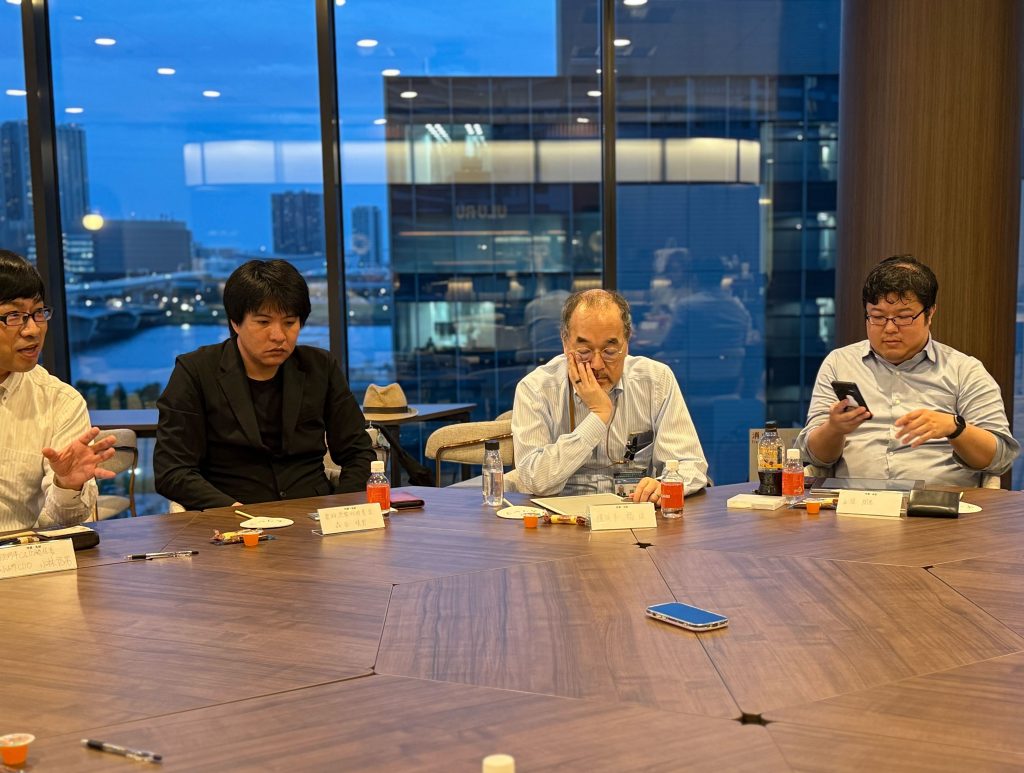
これらに加え、少しでもギャップを生まないための方法として、実践に基づいた下記のような意見もあがります。
「計画を立てることが目的化しないためにも、工程の可視化は必要です。現在地が目に見えれば、『次はこうしていきましょう』という話にもつながります」
「プロジェクトのようにゴールのある施策であれば、職員の皆さんは動きやすいものの、『スマートシティをどう実現するのか』のようなものはゴールがよく分かりません。この場合は、計画を細かくプロジェクト化し、逆引きで何をしたらいいのかマイルストーンを置くと動きやすくなります。データの活用も一つの手です。『医療費を何%削減しよう』のような話に落とし込むと動き出すんですよね」
また、ギャップを生まない準備は目標の設定段階から始まっている、と説く参加者も。
「いわゆる抽象レベルが高い状態で合意を得ているうちは、優先順位や重要度に対し、一人ひとりがちょっとずつ違った見方をしていると思うので、「あるべき姿」に違いが生まれてしまいます。それを解消してから目標設定をしないことにはなかなかうまくいきません。そのためには、個人の考えや思いを見えるようにして、お互いに情報を出しながら違いを埋めていく。すると、最終的に目標を五つの中から三つ選ぶにしても、ポイントを絞った会話ができるのでわりかし短い時間で合意が取れると思います」
ビジョンは明確に、計画は柔軟に

また、DX計画で前提としておく必要があるのは、テクノロジーの進化です。計画時には無かった有用なプロダクトが出てきたとしても、アクションプランをガチガチに固めてしまっては身動きが取れず、画期的な施策につながる機会を逸することにつながりかねません。
この点、「ビジョンと実行計画は完全に分けています。たとえば、業務改善手段としてAIが出てきたとしても、ビジョンには手段を書いていないので変える必要はありません。あくまでも計画どおり実行していく設定のもと、進捗のギャップや、新しい手段が出てきた場合にはそれらを柔軟に取り込んでいくことを想定して計画しています」の声に代表されるとおり、ビジョンは確固たるものを掲げるものの、行動計画は都度、最適解を選択できるようにしている、という共通の見解が示されました。
以上、第3回も打ち解けた雰囲気のなか、各参加者からは具体的な実例にCIO補佐官の役割や考えを織り交ぜた、示唆に富んだ話が多く飛び交いました。
そのなかでも印象的だったのは、「計画をつくることよりも重要なのが、プロセスです。実現したいことは何なのか、優先度の高いものはどれか、絶対に変えないものと柔軟に変えていくものは何か、こうした部分を担当職員と認識を合わせて進めていく視点は外せません」という言葉。計画をつくるのが人であれば、実行もまた人がするものです。携わる人の納得感や、目的に対する共有認識があってこそ、計画が進んでいくことを改めて確認できる場にもなりました。
ディスカッションに続いて、プログラムはネットワーキングへと移ります。この場でも、今回のテーマをさらに深く掘り下げる様子や、積極的に情報交換を行う姿が見られました。

次回予告:「C-hub Meetup Vol.5」開催決定!
次回のMeet upは2025年9月19日(金)18時からスタートです!
第5回は、「成功したDX 施策/失敗したDX 施策」〜他自治体の取り組みから学ぶ〜をテーマに、引き続き、自治体事例の共有による学びと実践へのヒントを獲得できる場をつくってまいります。

うるるは引き続き、自治体DXのキーマンとなるCIO補佐官の方に向けて、情報交換やネットワーキングの機会を提供することで、自治体DXの底上げと促進を目指してまいります。

