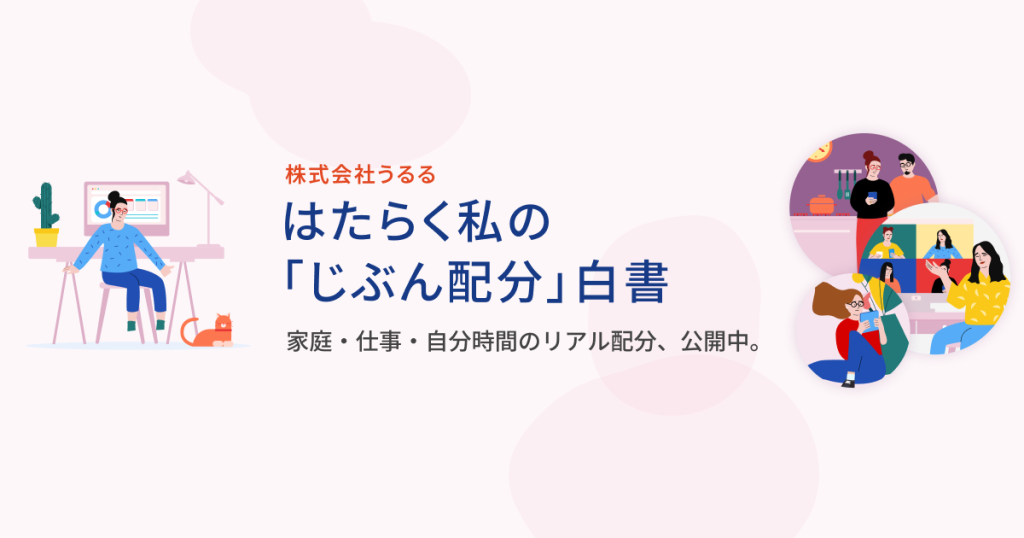欲しいものはトレードオフじゃない。完璧じゃなくていい、“心の補助輪”をつけて理想の「じぶん配分」を生きよう

ライフステージの変化のたびに、仕事や家庭との向き合い方に悩む、すべての女性へ──。
連載「はたらく私のじぶん配分」では、さまざまな葛藤や努力の先に、自分らしい心地よいバランスを見つけた女性たちのリアルなストーリーをお届けします。
この連載は、『はたらく私の「じぶん配分」』プロジェクトの一環として展開しており、さまざまな視点から実際の「じぶん配分」を可視化することで、すべての働く女性が「今の自分に合った働き方とは何か」を考えるきっかけを提供します。
そして、一人ひとりが「今の自分にとってのベストな配分」で働ける社会の実現を目指します。
『はたらく私の「じぶん配分」』特設サイトはこちら:
今回お話を伺ったのは、スタートアップ企業の副社長として、そして一児の母として走り続ける丹下恵里さん。そのキャリアの裏側で、彼女もまた「いい母親でいなきゃ」「デキるリーダーであるべき」と、自分自身に多くの役割を課し、もがき続けてきた一人でした。
そんな彼女を解放したのは、1歳になった娘さんのありのままの姿。完璧な誰かになることをやめ、自分にとっての「心の補助輪」を見つけた時、仕事も家庭も、すべてが繋がる心地よい「じぶん配分」が見えてきた丹下さん。完璧じゃなくていい──自分らしく、前へ進むためのヒントをお届けします。
目次
「母親だから」で諦めない。私を縛る“呪い”を解いたのは、1歳を過ぎた娘

──まず、現在の丹下さんにとって「仕事」「家庭」「ご自身の時間」のバランス、いわゆる「じぶん配分」は、ご自身でどのように感じていらっしゃいますか?
気持ち的には、結構いいバランスだなと思っています。もちろん、日々のタスクに追われて「ああ、もう!」ってなる瞬間はたくさんありますけど(笑)。
家庭では夫と対等に分担できています。私は株式会社mentoという会社で副社長をしているのですが、夫は元々新卒の同期でもあるので、お互いに仕事の状況を理解し、リスペクトし合える関係です。だから日々の忙しさも、家庭という一つのチームで乗り越えている感じですね。
──チームで乗り越える、素敵な関係ですね。差し支えなければ、丹下さんのとある1日のスケジュールを教えていただけますか?
朝は5時から7時の間に、娘が「イエーイ!」って言いながら起きてくるので、その声で目覚めます。そこから、自分の準備と娘の保育園の準備を大急ぎで進めて、8時半には家を出ます。
日中の仕事は、経営の意思決定からメンバーとの1on1、採用活動まで、本当にめまぐるしいですね。夕方6時頃に娘を保育園にお迎えに行って、そこからは怒涛の育児タイム。娘が寝た後の夜9時半頃から、残っていた仕事の続きをしたり、自分のためのインプットの時間にしたり。あっという間に1日が終わります。
──今の「いいバランス」に至るまでには、様々な葛藤があったかと思います。ご自身のキャリアと、母親であるという役割の間で、悩まれた経験はありますか?
私の実家は愛知の田舎のほうで、「女の子は愛嬌があればいい」という価値観が強い両親のもとで育ちました。今でも母から電話がかかってくると、「旦那さんにご飯ちゃんと作ってる?」「掃除ちゃんとしてる?」なんてよく言われます。
こうした環境で育ってきたからか、心のどこかでずっと「家庭をちゃんとやること」と「仕事で成果を出すこと」は両立できない、どちらかを犠牲にするトレードオフの関係にある、という思い込みがありました。特に子どもが生まれてからは、「母親なんだから、仕事はセーブするべきなんじゃないか」というプレッシャーを、自分自身でかけてしまっていたんです。
──その考え方が変わる、何かきっかけがあったのでしょうか。
娘が1歳を過ぎて言葉を話せるようになり、彼女の感情がわかるようになったことが大きかったですね。それまでの私は「社会からどう見られるか」「母親としてどうあるべきか」ばかりを気にしていました。でも、娘が自分の意思で「これがしたい」「これは嫌だ」と伝えてくれるようになって、私の視点がガラッと変わったんです。
悪気はないとわかっていても、周囲の人の何気ない一言に、深く落ち込むこともありました。当時の私には、まるで「母親なのに、仕事ばかりして」と言われているように感じてしまって。
でも、そんな風に悩んでいる私の気持ちとは裏腹に、娘は日々、自分の感情をストレートにぶつけてきてくれる。その姿を見ていたら、周りからどう見られるかとか、世間の言う「あるべき母親像」とか、全部どうでもよくなって。「今、この子が楽しそうか。笑っているか。それ以上に大切なことなんてないじゃないか」って。
そう思えた瞬間、仕事でいきいきと頑張ることも、娘にとって「かっこいいお母さん」でいることも全てが地続きなんだと、すとんと腑に落ちたんです。私を縛り付けていた「母親だから」という呪いが、娘自身のありのままの姿によって解かれたような、そんな感覚でした。
「すごいリーダーであるべき」。理想と現実の狭間で苦しんだ過去
──お子様が丹下さんを縛る「母親だから」を解放してくれたとのことですが、その他、これまでにどのような苦労や葛藤がありましたか?今を生きる上で、特に影響があった出来事があれば教えてください。
特に新卒で入社した1社目、リクルート時代は「べき論」に縛られて、理想と現実のギャップに苦しんでいた時期だったように思います。
というのも、配属されたのがリクルートの新規事業部門だったんです。新卒1年目からエグゼクティブに近い環境で働いていたのでまさに「すごいリーダー」たちを間近で見てきました。海外の投資先である、オーストラリアやシリコンバレーのスタートアップ経営者と会う機会もいただき、「理想のリーダー像」が良くも悪くも自分の中でどんどん膨れ上がっていって。
──錚々(そうそう)たる方々に囲まれていたのですね。
はい。一方で当時の私は、プレゼント動画アプリ『MINMOO(ミンムー)』というサービスを新規事業として立ち上げ、ありがたいことに社内で表彰もいただいたのですが、事業計画もまともなものを作れていなかったですし、実際1年くらいでサービスは終了してしまいました。
「すごいリーダーであるべき」という高い理想と、それに全く追いついていない現実の自分。そのギャップを常に突きつけられているようで、苦しかったですね。
苦しいのは「個人の弱さ」のせいじゃない。心の補助輪をつけて、「ダサく、明るく、楽しく」進む
──ご自身を縛り付けていた、その「べき論」から、どのようにして抜け出していったのですか?
劇的な何かがあったというよりは、人との対話の中で、少しずつ氷が溶けていくような感覚でした。特に大きかったのは上司との1on1や、mentoでコーチングに出会ったことです。
それまでの私は、分厚い鎧を着込んで自分の弱さを隠すことに必死でした。でも、信頼できる上司やコーチに自分のバイアスや「こうあるべき」という思い込みを、客観的に指摘してもらう機会が増えていって、少しずつ変わっていきました。
最初のうちは「でも」「だって」と言い訳ばかりだったけれど、何度も対話を重ねるうちに、「ああ、私はずっと、自分自身が作った『すごいリーダー』という幻と戦っていただけなんだ」と認めることができたんです。
考え方が少しずつ緩和されていった結果、「ダサく、明るく、楽しく」という、自分にぴったりのリーダー像にたどり着いた、という感じですね。完璧じゃなくてもいい、格好悪くてもいい。そう思えるようになったことで、少しずつ「べき論」の呪縛から解放されていきました。
──当時の丹下さんのように、そうした「べき論」に苦しんでいる女性は今も多いと感じます。
本当にそう思います。でも、これは決して「個人の弱さ」の問題ではない、ということを強くお伝えしたいです。
例えば、仕事で成果を求められる一方で、家庭では家事や育児といった役割も自然と期待される、といったことは往々にしてありますよね。どちらも完璧にこなそうとすると、どうしても無理が生じてしまう。そうした構造的な難しさに、多くの方が直面しているのではないでしょうか。
だから、みんな何かしらの支えが必要だと思います。一人で抱え込まずに周りを頼ったり、客観的な視点をもらったりするような支えがあるといい。私のイメージでは、それは自転車につける「補助輪」に近いです。でも、大人になったら補助輪をつけてはいけないって、みんなどこかで“思わされている”ような気がしていて。
そんなことは全くないので、自分が自分らしく前に進んでいくために補助輪が必要なのであれば、堂々とつければいい。そんな「心の補助輪」が、私たちには必要なのだと感じています。
──「心の補助輪」って、素敵な表現ですね。
ありがとうございます(笑)。補助輪をつけて走ることは、決して恥ずかしいことじゃないんです。むしろ、自分にはどんな補助輪が必要で、どうすればもっとうまく乗りこなせるようになるだろうと前向きに考えていいんだよ、と伝えたいですね。

私にとっては、一番の味方でいてくれる夫がそれにあたります。一人で頑張ることをやめて、「助けて」と言えるようになった。夫は私の大切な「心の補助輪」です。
育休からの3ヶ月復帰。立場を気にせず「わからない」と正直に伝える
──出産や育休といったライフステージの変化、その当時の様子についても伺いたいです。
そうですね。私は育休を3ヶ月で終えて復帰したんですけど、その時は本当に大変でした。まるで転職初日のような、何もわからない状態に陥ってしまったんです。
──その状況を、どのように乗り越えていかれたのですか。
もう、とにかく「わからない」と恥ずかしがらずに言う、それだけでしたね。
これは個人的な話ですが、私、子どもを産んだら脳が完全に母親モードに書き換わると思っていたんです。でも、実際に復帰してみると、仕事の悩みも、自分の頭の中身も、産む前と全く変わっていなくて。「私、いい母親なのかなこれ」って、また別の悩みを抱え込んでしまって。
でも、そうした不安や葛藤も全部ひっくるめて、一つひとつ「大丈夫だよ」と言ってくれる仲間が周りにいてくれた。長く休めば良い母親、というのも一つのバイアスだと思いますし、私自身は3ヶ月で復帰したことに後悔はありません。やっぱり、自分の心のままに決めるのが一番いいな、と強く思います。
「この時代に生まれて、良かった」。潮目の中で見つける、私らしい生き方
──そうした丹下さんご自身のリアルなご経験も踏まえて、最後にもう少し広い視点でお話を伺えればと思います。丹下さんが今、変えたいと感じる社会の「思い込み」のようなものはありますか。
そうですね。これはあくまでも一個人の意見として聞いていただきたいのですが、あと10年ぐらいは働く女性は辛い思いをすることも多いだろうな、と思います。
──と、言いますと?
色々な制度が整ってきているとはいえ、まだ過渡期だと感じているからです。だからこそ、今まさに頑張っている方々が、少し不利な戦いを強いられている最中なのかもしれない、と。
──なるほど。一方で、そうした難しさがある中でも、この時代ならではの希望のようなものは感じますか?
ええ、もちろん。この時代に生まれてきて、とても良かったなって思っています。
確かに、特定のところだけを見ると辛くなることもあります。でも、例えば少し前の時代を思うと、社会は確実に変わってきていると感じますし、何十年後には今私たちが悩んでいることなんて、きっと問題じゃなくなる。そういう気がするんです。
何より、女性がリーダーとして「こんなことで悩んでいるんです」と発信すること自体が、ちゃんと社会的な価値になる。そう考えると、この潮目の時代に生まれることができて、私はすごく良かったと思えます。
──そんな「潮目の時代」を、私たち一人ひとりがより自分らしく、心地よく生きていくために、どのような心の持ち方が必要でしょうか。
もし今、「いい母親ってなんだろう」「いいリーダーであるべきなのに」と悩んでいる方がいたら、「他人を主語にして考えるのを、一旦やめてみませんか?」と伝えたいです。大切なのは、あなたがあなた自身の人生を、どうしたいか。
そして、ベストな「じぶん配分」とは、何かを諦めるためのトレードオフではない、と私は考えています。仕事も、家庭も、自分自身の時間も、全てが繋がって一人の人間を創っている。だから何も諦めなくていいし、堂々と色々な人の助けを借りて、自分だけの心地よいバランスを見つけていってほしいなと思います。