
日本の労働力不足問題の解決に向けた、うるるの挑戦 ~「埋蔵労働力資産」発表に込めた想い〜
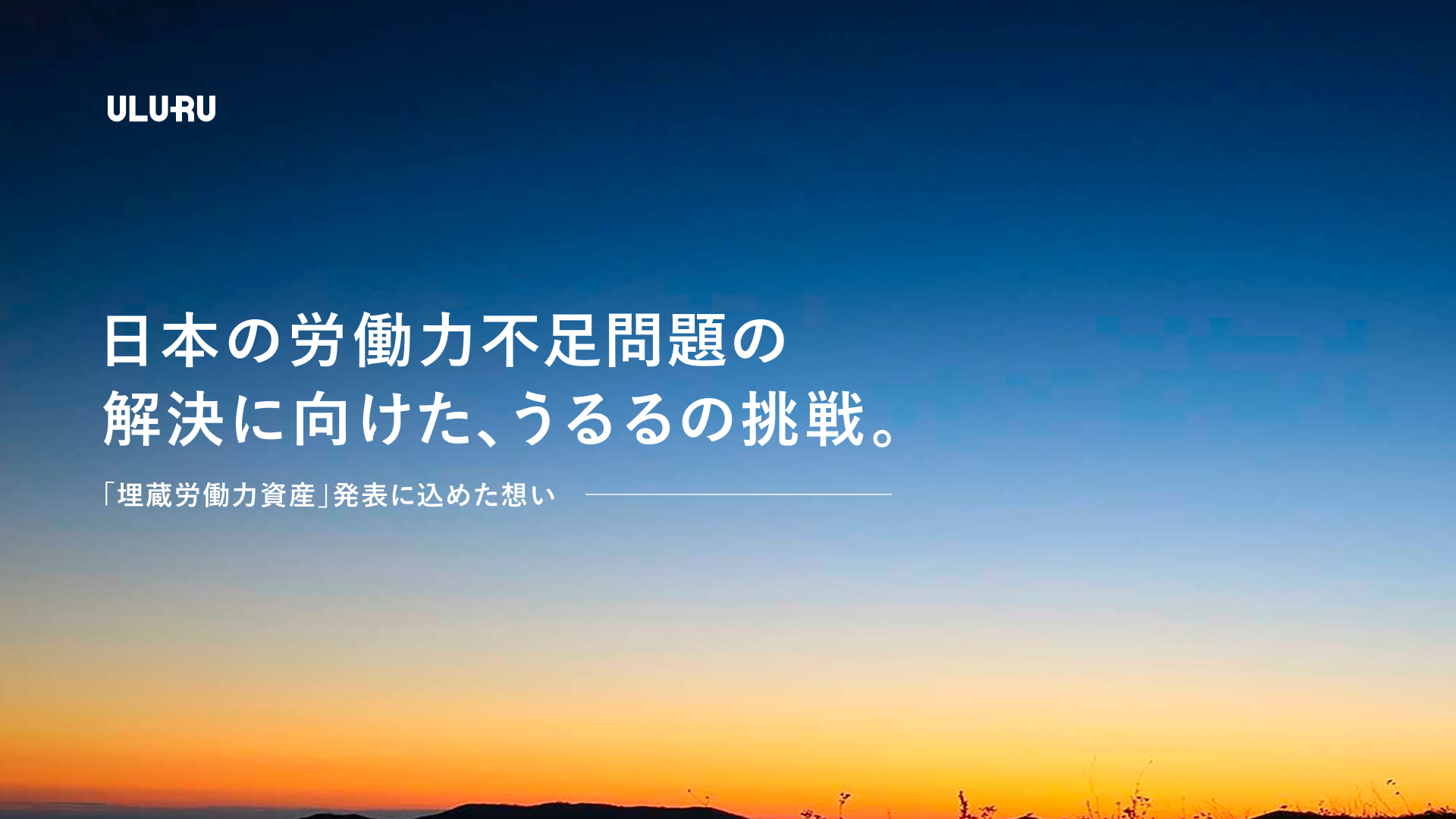
日本が抱える深刻な社会問題——労働力不足。
高齢化の進行、少子化による働き手の減少、そして急速なITやAIの進展により、日本の労働市場はかつてない変革期を迎えています。そんな中、うるるは 「埋蔵労働力資産」という新しい労働の概念を定義し、その経済価値を初めて試算しました。
—労働市場には、まだ活用されていない膨大な価値が眠っている。—
今回の試算では、その規模は 約135兆円 にも及ぶことが明らかになりました。この「埋蔵労働力資産」の存在を社会に示し、どう創出・活用できるかを考えることが、未来の労働市場を作るカギとなります。
本記事では、この135兆円というインパクトのある数字の背景や、今後の「埋蔵労働力資産」創出・活用について、株式会社うるる 代表取締役社長・星 知也へインタビューしました。
目次
労働力の新たな概念、「埋蔵労働力資産」とは?
ーー今年2月に「埋蔵労働力資産」の試算についての発表がありましたが、非常にユニークで新しい労働力の概念だなと感じました。改めて、概念や定義について教えてください。
星:今回私たちが発表した 「埋蔵労働力資産」とは、現在の労働市場において活用されていない、もしくは今後埋もれてしまう可能性がある労働力を指す概念です。
具体的には、
- 「埋もれている労働力」:時短勤務者やパート、フリーランス、休職者、未就業者(※1)のうち、労働意向があるにもかかわらず、現状以上に希望通りに就労できていない20~69歳(※2)の労働力
- 「埋もれゆく労働力」:ITやAIなどの最先端技術の導入による業務改革に伴い、直接的、間接的を問わず将来的(※3)に既存の業務が代替されることで生まれる労働力
です。
この二つの労働力は、労働力不足問題の解決はもちろん、日本の経済成長や持続可能な社会の実現においても重要な資産となり得ると考えています。
ーーなんだか明るい未来を感じさせますね。では、この「埋蔵労働力資産」の定義に至った背景を教えてください。
星:うるるは創業以来、育児や介護などの事情で、働きたくても働けない主婦層を中心とした未活用の労働力、すなわち「埋もれている労働力」を創出・活用してきました。
他方、近年、様々な業界でITやAIなどの最先端技術を活用したサービスの普及が進み、これまで人が担っていた既存の業務がIT・AIによって置き換えられつつあります。
今後さらに多くの業務がこれらの技術に置き換わることが予想される中、うるるは、IT・AIの進展による労働代替によって生じる「埋もれゆく労働力」が存在すると着目しました。
ーー「IT・AIの進展によって既存の業務が代替される」までは、これまでも注目されてきた話題ですが、その「代替された労働力をも活用すべき」という考え方は新しいですね。
星:そうですね。これまで「埋もれている労働力」を創出・活用してきたうるるだからこその独自の視点であると考えています。
ーーなぜ今のタイミングで「埋蔵労働力資産」の発表を決断したのでしょうか?
星: その背景には、今日本がまさに直面している「2025年問題」や、5年後にさらに深刻化されると言われている「2030年問題」があります。
昨今も人手不足のニュースをよく見かけますが、少子化の影響で約5年後には労働力不足がさらに深刻化することが予想されています。
だからこそ、今の段階で「埋蔵労働力資産」という概念を発表し、企業や社会全体でこの問題に向き合うことが重要だと考えました。
日本に眠る労働力の価値は、なんと135兆円!
ーープレスリリースで、「埋蔵労働力資産」の経済価値を発表されていましたね。試算の結果について詳しく教えてください。
※「埋蔵労働力資産」発表に関するプレスリリース:https://www.uluru.biz/news/14928
星: はい、今回の試算では、「埋蔵労働力資産」の規模は約135兆円にも達することが明らかになりました。
この金額は、
- 労働意向がありながらも、さまざまな理由から働きたくても働けない「埋もれている労働力」による「埋蔵労働力資産」:約15兆円
- IT・AIによって今後代替される可能性が高く段階的に「埋もれゆく労働力」による「埋蔵労働力資産」:約120兆円
を合算したものです。
ーー135兆円!その試算結果についてはどのように捉えていますか?
星: まず、とてもインパクトのある数字だと捉えています。135兆円は日本のGDPの約2割に相当します。「埋蔵労働力資産」をフル活用することができたら、日本経済へ大きな影響をもたらし、新たな成長機会を創出できる可能性を秘めていると、ポジティブに考えています。
ーーフル活用、とおっしゃいましたが、「埋もれている労働力」「埋もれゆく労働力」それぞれを創出・活用していく上でのカギは何だと考えていますか?
星:まず、「埋もれている労働力」については、現時点で十分に労働市場に参加できていない人々の存在が浮き彫りになりました。
今回の試算にあたってうるる独自で調査を行ったのですが、調査によると「現在よりも働きたい」と考えている人が多くいることがわかりました。(※4)その結果から、「希望する時間で働けていない」という課題も浮き彫りになっています。
具体的には、一人当たり一週間の「埋もれている労働力」は1.7時間あることが判明しました。
インパクトのある数字ではないものの、これはとてもリアルな数字だと捉えています。
また、休職・未就業者の20~40代・女性の79.3%が働く意向があり、労働市場に出れていない最大の理由は、「出産・育児(33.9%)」であること、さらには「心身の障がい(16.9%)」「自身の傷病(11.9%)」など、ライフイベントや健康上の理由が大きな要因となっていることが調査より判明しました。
これらの結果から、「時間の未活用」という観点では、既に働いている人が希望に応じて労働時間を増やせる仕組みの整備が求められます。
「労働市場に参加できていない人手」の観点では、柔軟な働き方を提供、労働市場への段階的な復帰など、仕組み作りが重要であるといえます。
ーー社会制度のアップデートなどの必要性が示唆されたということですね。では「埋もれゆく労働力」についてはいかがでしょうか。
星:「埋もれゆく労働力」については、「IT・AI技術によってどの程度の業務が代替されると感じているか」調査を行った結果、「単純作業」「定型作業」の代替可能性について、50%以上と回答した割合が約5割に上り、反復的な業務の自動化が進みやすいと感じている人が多いことがわかりました。
一方で、「対人業務」の50%以上代替可能と回答した割合は36%、「創造業務」でも50%以上代替可能とした割合が34.2%といずれも30%台にとどまり、IT・AIでは補完が難しい特性があることが示されています。
この結果についてはおおよそ予想通りであったものの、さらに細かく年代や性別でクロス集計をしていくと面白い傾向が見られました。
同じ業務でも年代や性別によってAIに対する受け止め方が異なり、IT・AIによる代替可能性の認識には個人差が大きく、人とAIの業務範囲の境界が明確ではないことが示唆されていました。
要するに、「どの業務が代替されるか」を一義的に定義するのは難しいということです。
つまり、「埋もれゆく労働力」を創出・活用するには、まず、人が行うべき業務とテクノロジーが担うべき業務を適切に判断し、切り分ける必要があるということ。
そして、自社の業務の棚卸をし、社内対応と外部リソース活用を判断することが「埋もれゆく労働力」創出・活用するカギであるといえます。
最大限の創出・活用を目指して
ーーこれらの結果をふまえ、うるるとして「埋蔵労働力資産」の創出・活用に向けては具体的にどのような取り組みを進めていく予定ですか?
星:はい。まず、うるるはこれまでも労働力不足問題の解決のために、人とテクノロジーのチカラを見極めた「適切な再分配」を軸にさまざまな事業を立ち上げ、成長を継続させてきました。
そこには一貫して、「人手を補う」だけではなく、「今ある労働力を最大限に活用することが重要である」という考え方があります。
そのためには、効率化できる業務にはITやAIの力を積極的に活用し、人が本来注力すべき業務に集中できる環境をつくることが不可欠です。それが、企業の競争力を高めると同時に、私たちのビジョンである労働力不足問題の解決、そして人がより豊かに働ける社会の実現につながると考えています。
今後も私たちは、こうした視点を軸に、さまざまな業界でのサービス展開を進めていきたいと思っています。
ーーこれまで取り組んできた領域を、「埋蔵労働力資産」という概念のもとでさらに強化していくイメージですね。サービスの展開以外で、「埋蔵労働力資産」を軸にした取り組みの予定はありますか?
星:はい、現段階で検討している具体的なアクションとしては、以下の3つが挙げられます。
1.ビジネスコンテストの開催
「埋蔵労働力資産」を創出・活用する新たなビジネスモデルを生み出すため、企業や起業家を対象にしたビジネスコンテストを企画。
2.出資・M&A
「埋蔵労働力資産」を創出・活用する企業やスタートアップに対して、うるるが出資を行い、支援する仕組みを検討。
3.政府への提言(官民連携)
「埋蔵労働力資産」の創出・活用を推進するため、政府や自治体と連携し、政策提言を行う。
ーー他社との連携が増えていきそうでワクワクしますね。
星:そうですね。これまでにない新たな取り組みが増えていくので、今後のうるるの取り組みをぜひ楽しみにしていただきたいです。
「埋蔵労働力資産」という概念を、実際に社会に価値を生み出す仕組みへと変えていくことが私たちの目標です。
そのためには、「埋蔵労働力資産」の創出・活用はうるる1社が取り組むものではなく、日本社会全体で取り組む必要があると考えています。
単なる定義や試算にとどめないためにも、うるるが旗振り役となり、積極的に推進していきます!
ーー星社長ありがとうございます。ここまでお話を伺って、「埋蔵労働力資産」は、労働力不足が深刻化する中でも、日本の未来に希望を感じられる、新しい労働力の概念だと感じました。
星:そうですね。私たちも、「埋もれている労働力」の創出・活用には、まだまだ多くの可能性が眠っていると考えています。
また、IT・AIの進展によって業務が自動化されることで生まれる「埋もれゆく労働力」にも注目しています。繰り返しになりますが、これは単に置き換えられるものではなく、新たに活かすべき貴重な労働力だと捉えています。
「労働代替=悪」という捉え方ではなく、テクノロジーによって人の力が再配置されることにこそ、新しい価値がある。
「埋蔵労働力資産」は、人口減少が避けられないこれからの日本にとって、新しい成長と共生のヒントになり得る概念だと信じています。
うるるは今後も、この視点を軸に、労働力不足という社会課題の解決に挑み続けます。
「埋蔵労働力資産」は、その経済インパクトからも単なる概念ではなく、日本の未来を左右する重要なテーマだということが伝わるインタビューでした。
今後、うるるはこの概念を社会に浸透させ、企業・政府・個人が一体となって活用していくための仕組み作りに取り組んでいきます。
「埋蔵労働力資産」の創出と活用が進めば、日本の労働市場はより柔軟で多様な形へと進化し、新たな価値創出の可能性が広がるでしょう。
この挑戦の先にどんな社会が築かれていくのか、これからのうるるの動向に、ぜひご注目ください!
■注釈
※1 休職者・未就業者は、「現在の職業」に関する設問で「専業主婦・主夫」、「リタイア」、「無職」と回答した人を対象としています。(うるる実施 「埋蔵労働力資産」の算出調査(2025年))
※2 労働力の中核を担っている20~69歳を対象(参考:「労働力調査における20~69歳の年齢区分の追加について」 総務省統計局 2019年)
※3 将来的・・・現在~2030年を想定
※4 現在の所定労働時間と今後希望する所定労働時間に関する設問で、それぞれの平均数値を算出。今後希望する所定労働時間の方が多い結果(うるる実施 「埋蔵労働力資産」の算出調査(2025年))

